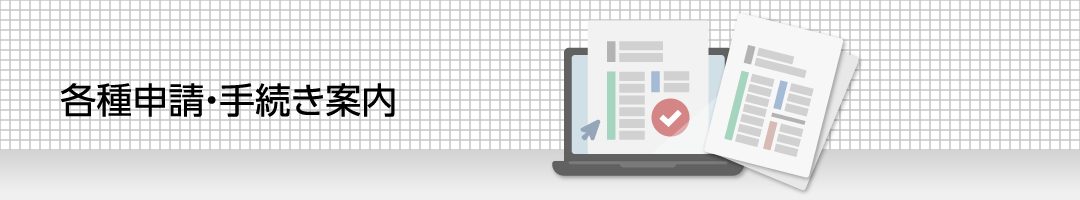本文
予防接種
予防接種とは
はしかや百日せきのような感染症の原因となるウイルスや細菌または菌が作り出す毒素の力を弱めて予防接種液(ワクチン)をつくり、それを体に接種して、その病気に対する抵抗力(免疫)をつくることを、予防接種といいます。 「予防接種」に使う薬液のことを「ワクチン」といいます。
すべての病気に対してワクチンがつくれるわけではなく、細菌やウイルスなどの性質によってできないものもあります。
定期予防接種
予防接種法に基づいて、市町村の責任において行われるもので、公費(無料)接種です。 対象予防接種の種類、接種年齢も決まっています。ただし対象年齢をはずれて、接種されたものは定期接種とはみなされず、自己負担となる場合もあります。
定期予防接種
ジフテリア(D)
百日せき(P)
破傷風(T)
急性灰白髄炎[ポリオ](Ipv)
麻しん[はしか](M)
風しん[三日はしか](R)
日本脳炎
結核(BCG)
ヒブワクチン
小児肺炎球菌[7価結合型]
子宮頸がん[Hpv]
水痘(みずぼうそう)
B型肝炎[HBV]
ロタウイルス(※)
※令和2年10月1日より定期予防接種となります
海外渡航のための予防接種について(厚生労働省検疫ホームページ)<外部リンク>
個別接種(定期予防接種)
| 種類 | 対象年齢 | 回数 | 間隔等 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 個 別 |
DPT-Ipv (4種混合ワクチン) D‥ジフテリア P‥百日咳 T‥破傷風 Ipv‥不活性ポリオ |
I期 | 初回 生後2ヶ月~7歳半未満 (標準:2か月~1歳) |
3回 | 20日以上の間隔をおく (標準:20~56日の間隔) |
| 追加 初回接種(3回目)の後 1年~1年半後 |
1回 | ||||
| Ii期 | 11歳から13歳未満 | 1回 | |||
| MR 麻疹(はしか) 風疹(三日はしか) |
I期 | 1歳~2歳未満 | 1回 | ||
| 2期 | 小学校就学前の1年間 | 1回 | |||
| 日本脳炎 | I期 | 初回 6ヶ月~7歳半未満 (標準:3歳) |
2回 | 6日以上の間隔をおく (標準:6~28日の間隔) |
|
| 追加 初回接種(2回目)の後 6か月以上の間隔をおく |
1回 | (標準:おおむね1年後) | |||
| 2期 | 9歳~13歳未満(標準:9歳) | 1回 | |||
| ヒブワクチン | 生後2か月~6か月で接種開始 | 初回:3回 追加:1回 |
初回:27日以上の間隔をおく(標準27~56日の間隔) ※初回接種は1歳になる前までに終えること 追加:初回終了後、7か月以上の間隔をおく(標準:7~13か月の間隔) |
||
| 生後7か月~11か月で接種開始 | 初回:2回 追加:1回 |
||||
| 1歳~5歳未満 | 1回 | ||||
| 小児用肺炎球菌ワクチン | 生後2か月~6か月で接種開始(1) | 初回:3回 追加:1回 |
初回:生後24月に至るまでの間に27日以上。 但し2回目以降の接種が生後12月を超えた場合、3回目の接種は行わない。 追加:初回終了後、60日以上の間隔をおき、1歳を終えて接種 |
||
| 生後7か月~11か月で接種開始(2) | 初回:2回 追加:1回 |
||||
| 1歳~2歳未満 | 2回 | 60日以上の間隔をおく | |||
| 2歳~5歳未満 | 1回 | ||||
| 水痘 | 1歳~3歳未満 | 2回 | 3か月以上の間隔をおく | ||
| BCG | (標準:生後5か月~1歳未満) | 1回 | |||
| B型肝炎 | 1歳に至るまでの間にある者 | 初回:2回 | 27日以上の間隔をおく | ||
| 追加:1回 | 初回1回目の接種から139日以上の間隔をおく | ||||
| ロ タ ウ イ ル ス |
ロタリックス | 生後6週0日後~24週0日後 | 2回 | 令和2年8月1日以降生まれで、令和2年10月1日(木曜日)以降に接種した場合は定期接種。 27日以上の間隔をおく ※1回目は生後14週6日後までに接種すること。 ※原則として1回目に接種した同一のワクチンで接種すること |
|
| ロタテック | 生後6週0日後~32週0日後 | 3回 | |||
- 従来のワクチン接種間隔に関しては、生ワクチンを接種してから次回接種まで27日以上、不活化ワクチンを接種してから次回接種まで6日以上の間隔をあけなければならない制限がありましたが、 定期接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日から接種間隔の一部が見直されることとなりました。
令和2年10月1日以降は、注射生ワクチン接種後の注射生ワクチン接種においてのみ27日以上の間隔をあけることとし、その他の接種間隔の制限はなくなりました。 ただし、あくまでも「異なるワクチンの接種間隔」における見直しであり、同一ワクチンを複数回接種する場合の接種間隔の制限は従来通りです。
予防接種(改正後の接種間隔イメージ図) [PDFファイル/125KB]
予防接種を受ける際に必要なもの
- 親子(母子)手帳
- 予診票
「予診票ダウンロード」から予診票をダウンロードすることもできます。
注意事項
一般的注意
- 当日は、朝からこどもの状態をよく観察し、ふだんと変わったところのないことを確認してください。
予防接種に連れていく予定をしていても、体調が悪いと思ったら、医師に相談の上、接種をするかどうか判断しましょう。 - 受ける予定の予防接種について、通知やパンフレットをよく読んで、必要性や副反応についてよく理解しましょう。
わからないことは会場で接種を受ける前に質問しましょう。 - 親子健康手帳(母子健康手帳)は必ず持っていきましょう。
- 予診票はこどもを診て接種する医師への大切な情報です。責任をもって記入するようにしましょう。
- 予防接種を受けるこどもの日頃の状態をよく知っている保護者の方が連れていきましょう。
なお、予防接種の効果や副反応などについて理解した上で、接種を同意したときに限り、接種が行われます。
予防接種を受けることができない者
- 明らかに発熱をしている者
- 重篤(じゅうとくな)急性疾患にかかっていることが明らかな者
急性で重症な病気で薬を飲む必要のあるような者は、その後の病気の変化もわかりませんので、その日は見合わせるのが原則です。 - その日に受ける予防接種の接種液に含まれる成分によって、アナフィラキシーを起こしたことがあることが明らかな者
「アナフィラキシー」というのは通常接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。
汗がたくさん出る、顔が急に腫れる、全身にひどいじんましんが出るほか、はきけ、嘔吐、声が出にくい、息が苦しいなどの症状に続きショック状態になるようなはげしい全身反応のことです。 - BCG接種の場合においては、予防接種、外傷等によるケロイドが認められる者
- BCG接種の場合においては、結核の既往のある者
- その他、医師が不適当な状態と判断した場合
上の(1)~(5)に当てはまらなくても医師が接種が不適当と判断した時はできません。
予防接種を受けた後の注意事項
以下に該当すると思われる人は、主治医がいる場合には必ず前もって診ていただいて予防接種を受けるかどうかをご判断いただき、受ける場合にはその医師のところで行うか、あるいは診断書又は意見書をもらってから予防接種に行きましょう。
- 心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気や発育障がいなどで治療を受けている者
- 過去の予防接種で、2日以内に発熱のみられた者及び発疹、じんましんなどアレルギーと思われる異常がみられた者
- 過去にけいれん(ひきつけ)を起こしたことがある者
けいれん(ひきつけ)の起こった年齢、そのとき熱があったか、熱がなかったか、その後起こっているか、接種するワクチンの種類は何かなどで条件が異なります。必ずかかりつけの医師と事前によく相談しましょう。
原因がはっきりしている場合には、一定期間たてば予防接種を受けることができます。 - 過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者
- ワクチンにはその製造過程における培養に使う卵の成分、抗生物質、安定剤などが入っているものもありますので、これらにアレルギーがあるといわれたことのある者
- BCG接種の場合においては、家族に結核患者がいて長期に接触があった場合など、過去に結核に感染している疑いのある者
予防接種を受ける判断を行うに際して注意を要する者
- 予防接種を受けたあと30分間は、接種会場でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。
急な副反応はこの間に起こることがあります。 - 接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう。
- 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、わざと接種部位をこすることはやめましょう。
- 接種当日は、はげしい運動はさけましょう。
副反応
通常見られる反応
1ワクチンの種類によっても異なりますが、発熱、接種局所の発赤・腫脹(はれ)、硬結(しこり)、発疹などが比較的高い頻度(数%から数十%)で認められることがあります(各病気の「ワクチンの副反応」の項を参照)。 通常、数日以内に自然に改善するので心配は不要です。
重い副反応
予防接種を受けたあと、接種局所のひどいはれ、高熱、ひきつけなどの症状があったら、医師の診察を受けてください。 お子さんの症状が予防接種後副反応報告基準に該当する場合は、医師から市町村長へ副反応の報告がされます。
ワクチンの種類によっては、極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障がいなどの重い副反応が生じることもあります。
このような場合に厚生労働大臣が予防接種法又は結核予防法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。
(参考)紛れ込み反応
予防接種を受けたしばらく後に、何らかの症状が出現すれば、予防接種が原因ではないかと疑われることがあります。
しかし、よく検査をすると、たまたま同じ時期に発症した他の感染症などが原因であることが明らかになることもあります。
これを「紛れ込み反応」と言います。
万が一健康被害が生じた時はどうなるの?
定期予防接種による健康被害が生じた場合に、厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済制度の給付の対象となります。 任意接種を受け健康被害が生じたときはPmda(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)による救済制度があります。
外部リンク
予防接種健康被害救済制度とは[厚生労働省HP]<外部リンク>
指定医療機関一覧表(近隣:令和6年4月1日時点) [PDFファイル/307KB]
※このリストに掲載されていない医療機関でも、県内他地区の医師会に加入し、予防接種受託医療機関であれば予防接種は可能です。 その場合は必ず医療機関へ確認し、予約してください。
予診票ダウンロード
予防接種を受ける際に必要な予診票は、接種履歴を確認し対象時期にご自宅へ郵送しております。 親子健康手帳の予防接種履歴にて未接種の場合で、定期接種の対象期間であれば、こちらからダウンロードしてご使用いただくこともできます。
※予防接種は、体調が良い時に受けるのが原則です。ご利用は必ず体調の良い時に!
※以下それぞれをクリックするとPDF形式でダウンロードできます。
1 Hib予防接種予診票 [PDFファイル/89KB]
2 肺炎球菌予防接種 [PDFファイル/70KB]
3 B型肝炎予防接種予診票 [PDFファイル/93KB]
4 四種混合予防接種予診票<ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ> [PDFファイル/92KB]
5 ポリオ予防接種予診票 [PDFファイル/91KB]
6 BCG接種予診票 [PDFファイル/64KB]
7 MR予防接種予診票(12~24月用)<麻しん・風しん> [PDFファイル/86KB]
MR予防接種予診票(5~6歳用)<麻しん・風しん> [PDFファイル/89KB]
8 水痘症予診票(12~36月用) [PDFファイル/90KB]
9 日本脳炎予防接種予診票(7歳半未満用) [PDFファイル/90KB]
日本脳炎予防接種予診票(9歳~13歳未満用) [PDFファイル/81KB]
日本脳炎予防接種予診票(特例) [PDFファイル/93KB]
10 DT予防接種予診票(11歳~13歳未満用)<破傷風・ジフテリア> [PDFファイル/79KB]
11 ロタウイルス予防接種予診票※令和2年8月1日生まれで、令和2年10月以降の定期接種用 [PDFファイル/98KB]
12 ヒトパピローマウイルスウイルス感染症予防接種予診票 [PDFファイル/108KB]
13 五種混合予防接種予診票<四種混合+Hib> [PDFファイル/70KB]